
歌人としての源實朝は、賀茂真淵に発見されたと言われる。これに対して小林秀雄は、『實朝』の冒頭を次のように書き起こしている。
芭蕉は、弟子の木節に、「中頃の歌人は誰なるや」と問はれ、言下に、「西行と鎌倉右大臣ならん」と答へたそうである(俳諧一葉集)。言ふまでもなく、これは、有名な眞淵の實朝発見より余程古いことである。
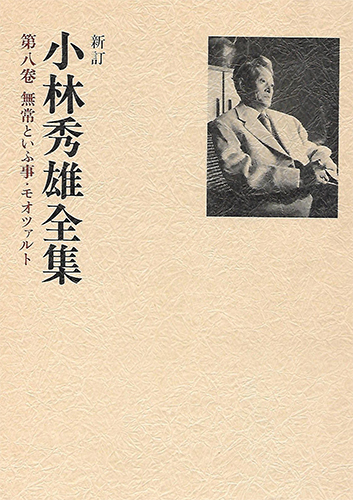
▲『小林秀雄全集8(實朝)』より。『モオツァルト・無常という事』 (新潮文庫)所収が求めやすい。
鎌倉右大臣とは、鎌倉三代将軍となった源實朝の官職名である。芭蕉が二人目の實朝発見者であるならば、三人目は正岡子規ということになるだろう。
子規は實朝を発見することで、日本の短歌を変えた。彼は1867年10月に生まれて1902年9月に死んだから、ちょうど35年の生涯だった。この生涯で短歌革新にかけた年月は10年間という短期日だった。
子規は1892年(明治25年、25歳)で俳句革新に乗り出し、続いて短歌革新に乗り出したのは1898年(明治31年、31歳)と思われる。いずれも「日本」という新聞が舞台であった。子規と新聞「日本」との関係については、司馬遼太郎の『坂の上の雲』に詳しい。
子規はいったん東京にもどり、この年の十一月九日母と妹をむかえるべく東京を発ち、神戸までゆき、ここで落ちあって十七日帰郷した。翌日、羯南がやってきて、「あなたの入社が決定しましたよ」と、吉報をもたらした。羯南が社長になっている新聞「日本」に入社するという件である。
(『坂の上の雲』司馬遼太郎)
羯南とあるのは陸羯南(くが・かつなん)のことである。日本新聞社の社長兼主筆。当時の西洋崇拝の風潮は、ほとんど国を挙げての傾向であったようだが、羯南はこれに激しく抵抗し、政府を激しく糾弾した。そのことで民族派と言われるようになったが、むしろ功績は、近代ジャーナリズムの先がけとなったことだろう。その羯南が25歳の子規に次のように言う。
別にこれというほどの仕事も無いから、いやな時は出勤しなくてもよろしい、その代り月俸は15円である。社の経済上予算が定まっているので、本年中は致し方が無いが、来年になれば多少何とかなるであろう。それまでのところ足りなければ自分が引受けるから。
(同書)
この鷹揚さが子規の心を大きく動かした。子規が叔父の大原恒徳に宛てた手紙にはこうある。
尤我社之棒給にて不足ならば他の国会とか朝日新聞とかの社へ世話致し候はば三十円乃至五十円位之月俸は得らるべきに付其志あらば云々と申候へども私はまづ幾百円くれても右様の社へは入らぬ積に御座候。
子規は、国会でもなく朝日新聞でもない、羯南に率いられた硬派の小新聞社に入ったことで、彼の文芸を表現するメディアを得ることになった。
新聞「日本」はたびたび発行停止処分になった。その間の収入を得るために「小日本」という新聞を出したというから、羯南という人のユーモア感覚も相当なものだ。「小日本」の編集責任者には、26歳の子規が就いた。
子規は新聞「日本」で、「歌よみに与ふる書」を10回にわたって連載した。
貫之は下手な歌よみにて『古今集』はくだらぬ集に有之候
(『再び歌よみに与ふる書』正岡子規)
こう切って捨てた子規は、その証拠として凡河内躬恒(おおうしこうちのみつね)の歌を挙げる。『古今集』に収められたもので『百人一首』でもおなじみの歌だ。
心あてに折らばや折らむ初霜の置きまどはせる白菊の花
意味はだいたい読んだ通りだと思うが、「一面に霜が降りてどれが白菊かわからないくらいだ。白菊を折ろうというなら、雪と見分けがつかないので見当をつけて折ってみようか」といったところか。
子規は、この歌には嘘がある、初霜が降りて白菊の花が見えなくなることはない、些細なことを大げさに述べすぎる、無趣味である、と難じた。その一方で、良歌の例として挙げられたのが源實朝の歌である。
時により過ぐれば民の嘆きなり八代竜王雨やめたまへ
子規は鎌倉三代将軍實朝の真心より出た勢いを善しとし、この歌に万葉の影響を読み取った。
いくつかの實朝年譜に見ると、上の歌は1211年7月15日に作られ、實朝が藤原定家から秘蔵の万葉集を手に入れたのは1213年11月8日とある。實朝が万葉に触れたのはそれ以前のことではあろうが、子規の例示には少しムリがあるかも知れない。
小林秀雄の見方はこうだ。『實朝』の中で子規の解釈に触れ、次のように疑義を呈している。
子規はこの歌を評し、「此の如く勢強き恐ろしき歌はまたと有之間敷、八大龍王を叱陀する處、龍王も懾伏致すべき勢相現れ申候」(歌よみに與ふる書)と言つてゐるが、さういふものであらうか。子規が、世の歌よみに何かを輿へようと何かに激してゐる様はわかるが、實朝の歌は少しも激してはをらず、何か沈鬱な色さへ帯びてゐる様に思はれる。僕には、懾伏した龍王なぞ見えて來ない、「一人奉向本奪」作者が見えて來るだけだ。まるで調子の異つた上句と下句とが、一と息のうちに聯結され、含みのある動きをなしてゐる様は、歌の調とか奏とかに關する、作者の異常な鋭敏を語つてゐるものだが、又、それは青年将軍の責任と自負とに揺れ動く悩ましい心を象つてもゐるのであつて、眞實だが、決して素朴な調ではないのである。個々の作歌のきれぎれな鑑賞は、分析の精綴を衒って、實朝といふ人問を見失ひ勝ちである。
(『實朝』小林秀雄)
しかし子規が檄のように書いた『歌よみに与ふる書』は、多くの歌人や歌人候補に、「万葉へもどれ」という大きな指針を与えたばかりでなく、近代日本に短歌の隆盛をもたらした。
2020/12/26 NozomN